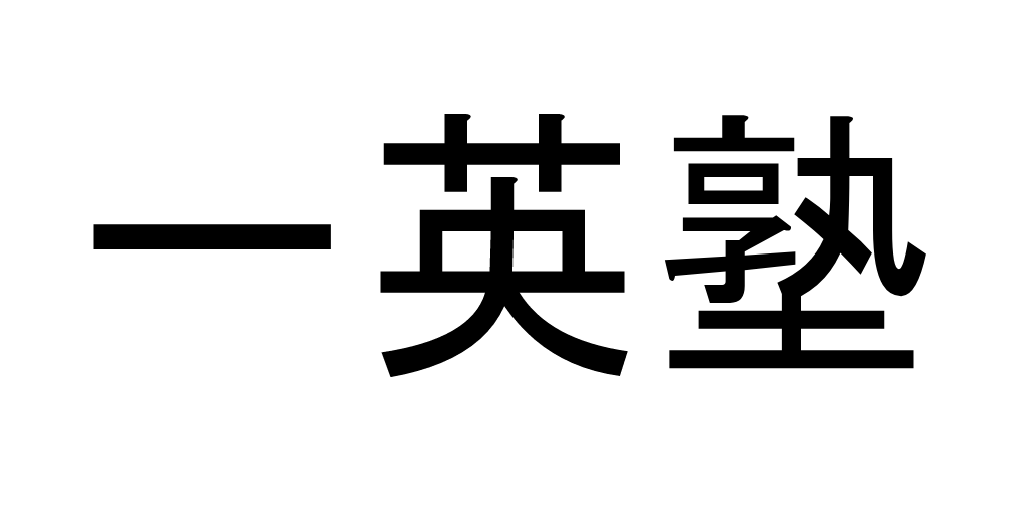今回は、勉強における、
・できる
・できない
・わかる
・わからない
の間のグラデーションについて見ていきます。
当然ですが、学校・学習塾・予備校・各種スクールなどで、「できる」「できない」「わかる」「わからない」という言葉は、当たり前のように飛び交います。
フワッとしている
ですが、意外と、どの程度「わからない」のか、どの程度「できない」のかがフワっとした状態で使うことがよくあります。
あるいは、生徒・保護者・先生の間で、この辺の程度・ニュアンスが、うまく伝わっていないということもよくあります。
できなかったところ?
つい、
「できなかったところを復習しておきましょう。」
と言いがちです。
現に、私もよく言います。
「なるほど。そうか!できなかったところを復習しておけばいいのか。」
と聞いて、適切に復習できる場合もありますが、そうでない場合もあります。
わからないところ?
あるいは、
「わからないところはありませんか?」
「わからないところを教えてください。」
というやり取りも、当然ながら頻繁に行います。
なんとなく流れと勢いでいけてしまうこともありますが、「どの程度」「わからない」のか、「どの程度」「わかる必要があるのか」がズレていると、これも、ちょっとおかしなことになってしまいます。
というわけで、今回は、改めて「できる」「できない」「わかる」「わからない」の間のグラデーションを見ていきます。
「できる」の
グラデーション
勉強では、
一口に、「できるところ」「できないところ」と言っても、
1 スムーズにできるところ
2 時間をかけてできるところ
3 わかっているが、ミスをしてしまうところ
4 言われればわかるところ
5 今の段階では難しすぎて説明を聞いてもなかなかよくわからないところ
というようにグラデーション・段階があります。
これは、筆者の分類ですので、人によって、もっと細かかったり、もっと別の分け方もできます。いずれにしても、「できる」「できない」「わかる」「わからない」にはグラデーションがあり、0か1かではないと意識することが大切です。
イメージ
具体的には次のようなイメージです。
1 スムーズにできるところ:
これは、問題や内容を見た瞬間に、すぐに解答や理解ができる部分です。十分な知識や理解があり、すぐに取り組むことができます。
2 時間をかけてできるところ:
この部分では、問題や内容を理解するのに少し時間がかかるかもしれませんが、時間をかけて取り組むことで解答や理解ができます。十分な学習や練習を通じて、スキルや理解を向上させることができます。
3 わかっているが、ミスをしてしまうところ:
ここでは、問題や内容については理解しているものの、ミスをしてしまう可能性があります。慎重な取り組みや注意深いチェックを行うことで、ミスを減らすことができます。
4 言われればわかるところ:
この部分では、説明やヒントを確認すれば理解することができます。問題に取り組む前に、学習内容・説明をしっかり確認することで、解答や理解が進むことがあります。練習をすすめることで、事前の確認・ヒントなしでできるようになっていきます。
5 今の段階では難しすぎて説明を聞いてもなかなかよくわからないところ:
この部分は、まだ難しい内容であり、現時点では説明を聞いても完全に理解することが難しいです。この場合は、その前段階の基礎的な知識やスキルの習得に重点を置き、段階的に理解を深めていく必要があります。
これらのグラデーションを意識することで、自分の理解度を把握し、適切な学習方法やアプローチを選択することができます。
つい、5の部分に焦点を当てがちです。
しかし、優先してやるべきなのは2~4です。
2~4の完成度を高めていくことが、理解を深め、得点をアップさせるカギとなります。
なぜ難しすぎるところに焦点をあてるか?
なぜ「5 今の段階では難しすぎて説明を聞いてもなかなかよくわからないところ」に焦点を当ててしまうかというと、「4 言われればわかるところ」は、言わればわかるので、もう「わかったもの」として先に進んでしまいがちだからです。
本当に焦点を当てるべきは
ですが、本当に大切なのは2~4の部分です。
できているが、ちょっとあやしい部分。
できているようでできていない部分。
わかっているようでわかっていない部分。
このあたりに焦点を当てて、練習をしたり、理解を深めていくことで、学習内容の完成度・理解度が上がります。
すると、「5 今の段階では難しすぎて説明を聞いてもなかなかよくわからないところ」も、やがてスムーズに理解ができるようになります。練習と理解を重ねることで、「5」→「4 言われればわかるところ」に降りてくるわけです。
以上を踏まえて、いくつかの科目・分野で見ていきます。
数学・計算
数学の計算問題において、「できるところ」と「できないところ」「わからないところ」は以下のようなグラデーションがあります。
1 スムーズにできるところ:
これは、問題を見た瞬間に即座に解答できる部分です。計算手順や概念がしっかりと理解されており、スムーズに解くことができます。
2 時間をかけてできるところ:
この部分は、問題の解決には時間がかかるかもしれないけれども、理解はしていて解くことができます。計算や概念について、練習や反復を通じてスピードを向上させることができます。
3 わかっているが、ミスをしてしまうところ:
ここでは、問題の解決方法や概念について理解していますが、ミスを犯してしまう可能性があります。この部分を克服するためには、慎重な計算や注意深い解答作業が必要です。練習や反復を通じて、習熟することで、ミスを減らしていくことができます。
4 言われればわかるところ:
この部分では、他人から解説やヒントを受ければ理解できる状態です。自分自身で問題に取り組む前に、解説を確認することで、解答方法や概念の理解を深めることができます。練習をすすめることで、事前の確認・ヒントなしでできるようになっていきます。
5 今の段階では難しすぎて説明を聞いてもなかなかよくわからないところ:
この部分は、まだ難しい内容であり、現時点では説明を聞いても十分に理解することが難しいです。この場合は、基礎的な知識や解決方法をより習得する必要があります。時間をかけて学習を進め、段階的に理解を深めることが求められます。
これらのグラデーションを意識することで、自分の理解度を把握し、適切な学習方法やアプローチを選択することができます。
くりかえしになりますが、
つい、5の部分に焦点を当てがちです。
しかし、優先してやるべきなのは2~4です。
2~4の完成度を高めていくことが、理解を深め、得点をアップさせるカギとなります。
徹底した反復練習などを行い、内容を改めて理解し、完成度を高めていきます。
英語
あるいは、英語(特に英語のテストの問題)の場合は、次のようになります。
英語のテストの問題において、「できるところ」と「できないところ」は以下のようなグラデーションがあります。
1 スムーズにできるところ:
これは、問題や文章を読んだり、文法や語彙を理解したりすることがスムーズに行える部分です。言葉や文の意味をすぐに把握し、正確に解答することができます。
2 時間をかけてできるところ:
この部分では、問題や文章の内容を理解するのに時間がかかるかもしれませんが、十分な時間をかければ解答できます。文法や語彙の学習や練習を通じて、理解とスピードを向上させることができます。
3 わかっているが、ミスをしてしまうところ:
ここでは、問題や文の意味を理解していますが、ミスを犯してしまう可能性があります。注意深く読み、文法や語彙のルールを正確に適用することで、ミスを減らすことができます。これについても、基本事項を繰り返し確認したうえで、とにかく反復練習が必要です。
4 言われればわかるところ:
この部分では、他人からの説明やヒントを受ければ理解することができます。課題に取り組む前に基礎的な知識や解決方法を確認することが重要です。練習をすすめることで、事前の確認・ヒントなしでできるようになっていきます。
5 今の段階では難しすぎて説明を聞いてもなかなかよくわからないところ:
この部分は、まだ難しい内容であり、現時点では説明を聞いても完全に理解することが難しいです。この場合は、基礎的な知識の習得や文法や語彙の拡充を重点的に行い、段階的に理解を深めていく必要があります。
再び繰り返しになりますが、
つい、5の部分に焦点を当てがちです。
しかし、優先してやるべきなのは2~4です。
2~4の完成度を高めていくことが、理解を深め、得点をアップさせるカギとなります。
徹底した反復練習などを行い、内容を改めて理解し、完成度を高めていきます。
反復練習は、問題演習だけ、文字だけではなく、音声を繰り返し聞く、繰り返し音読する、英文の暗唱なども有効です。
まとめ
以上の内容はあくまでも一例です。
いずれにしても大切なのは、理解度にはグラデーションがあるの意識すること。時間がかかるもの・ついミスをしてしまうものを、いろいろな形で練習して、完成度を高めていくこと。これが、成績を効率よく上げていくコツの一つです。
ある程度勉強が得意でうまくいっている場合には、特に意識しなくてもうまくいきますが、苦手科目の場合、ちょっと調子が出ない場合は、このあたりを意識して学習を進めると、できるものが増えていき、モチベーションも上がっていきます。
高校生・中学生・小学生
“オリジナル
メソッド”
個別指導
一英塾




TEL:043-463-3003
一英塾(いちえいじゅく)勝田台校
勝田台駅から徒歩2分
千葉県佐倉市井野1544-31
なごみビル202