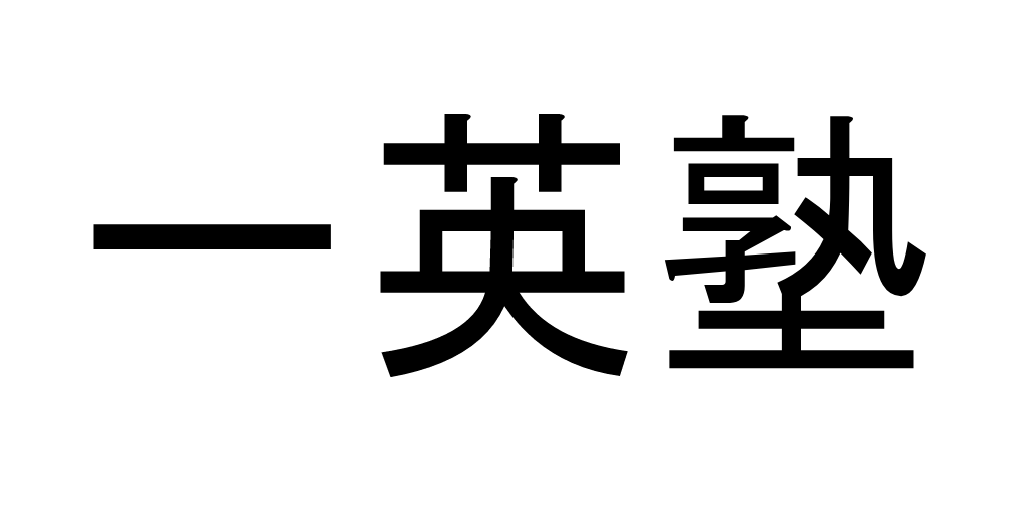今回は、問題集・参考書の使い方で、
「1冊を完璧にすること」
or
「何冊も使うこと」
のメリットとデメリット、どのようにバランスをとるべきかについて見ていきます。
メインとしては大学受験に関する話ですが、その後の専門的な勉強や資格試験の勉強にも応用可能な話になっています。
1冊vs何冊も
例えば、以下のような話をよく聞きます。
「教科書や問題集が難しいから、別の参考書・問題集をそろえていったら、参考書だらけで収集がつかなくなってしまった。やはり、1冊を完璧に仕上げることが大切なのか?」
「1冊完璧に仕上げようと頑張っているが、思うように進まない。あまり、いろいろな参考書に手を出しすぎるのはよくないと思うが、どうすればいいか?」
「必要に応じて別の参考書を使うことで、理解がグッと進み、効率よく学習することができた。」
「とにかく1冊の問題集を完璧に仕上げようと頑張ったら、しっかり実力がつき、成績もぐっと上がり、結果を出すことができた。」
さて、いったい、どうすればいいのでしょうか?
バランス
結論から言うと、上記の内容のバランスをとっていくことが大切になります。
自然にバランスがとれている場合もありますが、得意な場合でも、状況によりバランスが崩れて、何からどうしたらいいのかわからなくなってしまう場合が結構あります。その場合にも、以下のことを改めて意識していくことが大切です。
目的・メイン・サブ
いずれにしても、1冊・1分野を一定の水準で完璧にすることを目標にしつつ、必要に応じて、目的に応じて別のもので補う。これが大切です。
では、そのバランスをどのようにとっていくのか?詳しくみていきます。
それぞれの長所と短所
1冊にしぼる場合
メリット
徹底的な理解・一貫性・体系化:
一冊を選び、その内容に集中することで、そのテーマに関する理解を徹底的に深めることができます。順序立てて学習し、基礎から応用まで体系的に学ぶことで、知識の積み重ねが進みます。一冊を使うことで、情報の統一性と一貫性を保つことができます。
デメリット
情報の欠落や制約:
一冊の参考書だけに頼ると、必要な情報が欠けたり、より詳細な解説や応用例が不足している場合があります。一冊の参考書だけではカバーしきれないことがあります。また、自身の疑問点や誤解が解消されない場合があります。
複数冊を使う場合
メリット
トピックの補完と理解の深化:
複数の参考書を使うことで、トピックごとに情報を補完することができます。一つの書籍ではあまり解説がなされていない場合でも、別の書籍では、詳細な解説がされていたり、応用例や実践的なアドバイスが提供されている場合があります。それらを利用することで、より深い理解と応用能力を養うことができます。
デメリット
情報の過多と混乱:
複数の参考書を使うことで、情報の過多や混乱が生じる可能性があります。異なる書籍から大量の情報を得るため、どの情報にフォーカスすべきか迷ったり、情報の整理が難しくなる場合があります。これにより、学習の効率や効果が低下する可能性があります。
目標の分散と欠落:
複数の参考書を使うことで、学習の目標が分散されたり、一部の情報が欠落したりする場合があります。異なる書籍間でカバーされるトピックや内容が異なるため、全体像や一貫性を保ちながら学習することが難しくなる可能性があります。
解決法
では、どうすればいいのでしょうか?
目的・メイン・サブ
以下の3点に気をつけることで、効率よく学習をすすめることができます。
1、目標・目的と優先順位の設定
2、コアとなる1冊の設定
3、補完のための追加
目的・優先順位
学習の目的を明確にし、優先順位をつけることが重要です。どのトピックやスキルに焦点を当てるべきかを把握し、それに基づいて学習を進めます。
迷ったら、「何が当面の目標か」を確認します。
コアとなる1冊
まずは一冊のメインとなる本・コアとなる本を選びます。学校の教科書というのもアリです。一定水準で内容を網羅し、自分の今のレベルに合うことが大切です。この一冊を仕上げることで知識や理解を獲得し、しっかりと学習を進めます。
サブ・補完のための追加
一冊だけではカバーしきれない情報や視点を補完するために、他の参考書を利用します。
なぜそれを使うのか、目的を決めて利用することが大切です。
コア・メインとなる1冊はしっかりと使い切る一方で、補助的に追加したものは、必要な部分だけ確認するという使い方でOKです。
完璧に仕上げる本(または部分)と、補助的に使う本を、メリハリをつけて使い分けることが大切です。
少なすぎ?or多すぎ?
少なすぎ?
メインとして使っているものでは目標をカバーしきれていないと感じた場合は、どの程度カバーできていないくて、何を補う必要があるのかを、できる範囲で明確にしましょう。
また、目標以前に、メインとして使っているものを進めるので手一杯の場合は、とにかく今やっているものをしっかり仕上げることを第一に考えましょう。
多すぎ?
メインとして使っている本を進めるのが大変だと感じる場合は、どのように大変なのかをはっきりさせましょう。
部分的に難しすぎる場合は、進める内容を絞り込むことで、うまく進められます。
多くの問題集では、難易度に応じて何らかの区分け・印がついているので、その区分に応じて、基礎的なもののみを進めるということもできます。
自力ではそれほど解けないけれど、解答解説の意味はしっかりわかるという場合は、繰り返し学習を進めることで、内容を自分のものにしていくことができます。
それでもどうしても難しい場合には、メインとなる本自体をより易しいもの、より使いやすいものに変えることも必要です。
英文法の例
例えば、大学入試の英文法を学習する場合、
メインとなる1冊:
英文法・語法ヴィンテージ
(特に、前半の「文法」のセクション)
必要に応じてサブとして使うもの:
「肘井学のゼロから英文法が面白いほどわかる本」シリーズ
SKYWARD総合英語
総合英語Evergreen
など
という使い分けができます。
英文法・語法ヴィンテージ(Vintage)やスクランブル英文法・語法は、学校で集団購入して定期テストの範囲になっている場合も多いようなので、その場合は、これらをメインにしつつ、これらだけでは頭に入れにくい場合に、他の詳しい説明のもので部分的に補っていきましょう。
ヴィンテージやスクランブルなどの網羅系の英文法問題集を持っていない場合は、状況や目標によっては、べつのより易しいものをメインにした方がいい場合もあります。
英語長文の例
英語長文問題集は、ある程度単語と文法を仕上げてから進めましょう。
進めるにあたっては、英語長文問題集こそ、とにかく繰り返し復習をして完璧にしていくことが非常に重要です。
大学受験向けだけでも、「ソリューション」「ポラリス」「イチから鍛える」「レベル別」「全レベル」など多くの問題集が出ていますが、これらのシリーズの中からまずは1冊決めて、しっかり1冊仕上げることが大切です。問題を解き、解答・解説を確認し、その後、繰り返し音声教材を確認したり、音読などを繰り返し行い読み返していきます。
基本的に1冊の中で完結できますが、あえてサブとして使うものとしては、すでに持っている単語集をたまに参照したり、文法参考書を必要に応じて参照するといった形になります。
どう使うか?
どう仕上げるか?
いずれにしても、メインとなるものを「どのように」使い、どう仕上げ、自分のものにしていくかが非常に重要です。
目標・目的・優先順位を確認しながら進めていきましょう。
高校生・中学生・小学生
“オリジナル
メソッド”
個別指導
一英塾




TEL:043-463-3003
一英塾(いちえいじゅく)勝田台校
勝田台駅から徒歩2分
千葉県佐倉市井野1544-31
なごみビル202